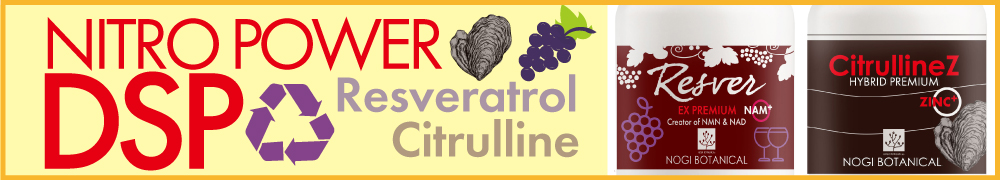米国では毎年50万人を超える高脂血症患者が心血管病で死亡しており、リスクを除去する研究が盛ん。
米国医学会会報(The Journal of the American Medical Association 2002)には
「オメガ3が心血管病のリスクを大幅に軽減する」という、80000人を超える追跡調査報告などもあり
青魚、鮭、サプリメントの摂食を推奨していますが、その作用メカニズム詳細は
解明されていませんでした。
高血圧、動脈硬化などに関係のない、突然の心筋梗塞、狭心症、脳卒中があります。
すでに2003年ごろには、突然死にはカルシウム非依存性の血管異常収縮があり、
それが高脂血で増加する細胞膜脂質の一つスフィンゴシルフォスフォリルコリン(sphingosylphosphorylcholine:SPC)の作用に起因するだろうという研究があり、
注目を集めていました。
この研究ではスフィンゴシルフォスフォリルコリンの活性を抑制する物質として
青魚の魚油脂肪酸として著名なEPA(エイコサペンタエ酸:eicosapentaenoic acid)が
同定されています。
高脂血症が関与する突然死
1.カルシウム非依存性異常収縮による突然死とSPCの発見
血管平滑筋の収縮・弛緩を制御している最も大きな因子は 細胞質のカルシウム濃度ですが、
このカルシウム依存性の血管収縮は、正常な血圧や血流の維持に重要な役割を果たしています。
これに対して、血管病の原因となるカルシウム非依存性の収縮機構もあります。
高血圧でない人、動脈硬化のない人が突然心筋梗塞をおこす、
くも膜下出血をした患者が、手術後に突然血管攣縮で死亡することなどから、
血管平滑筋にはカルシウム非依存性異常収縮があることが
一部の研究者に認識されていました。
[Blood Levels of Long-Chain n–3 Fatty Acids and the Risk of Sudden Death]
Christine M. Albert MD MPH Hannia at the Division of Preventive Medicine Brigham and Women’s Hospital、
The New England Journal of Medicine 2002
日本では山口大学の小林誠教授、岸博士らは、この異常収縮の原因物質として
スフィンゴシルフォスフォリルコリン(sphingosylphosphorylcholine)を同定しており、
SPCが、血管平滑筋の細胞質カルシウム濃度を変化させることなく、
酵素を介して異常収縮を引き起こすことを見出しています。
2.高血圧治療薬、狭心症治療薬の限界
これまでの高血圧治療薬、狭心症治療薬は、全て、カルシウム依存性の
正常収縮を抑制するもので、その治療効果には限界があり、投与によって血圧低下や
頻脈などの副作用を引き起こす事も多々ありました。
SPCの作用経路を明らかにすることは、正常収縮の経路を損なうことなく、
SPCをピンポイントで抑制できることに繋がります。
3.スフィンゴシルフォスフォリルコリン(sphingosylphosphorylcholine:SPC)とは
スフィンゴシルフォスフォリルコリンは細胞膜に存在するスフィンゴ脂質の一つである
スフィンゴミエリン(sphingomyelin)から生成されます。
近年、SPCは血液中にも存在することが報告され、注目されています。
この研究は血管平滑筋異常収縮の原因物質であるSPCを活性化させる物質、
あるいは活性を消失させる物質の追及といえますが、小林教授、岸博士らは
「血管平滑筋のSPC反応性に対するコレステロールの重要性と、細胞膜ラフトの関与の可能性」
「血管平滑筋におけるカルシウム依存性収縮およびカルシウム非依存性収縮に対するEPAの作用の違い」
などの二つの研究で、カルシュウム非依存性の血管平滑筋異常収縮を、魚油の天然シス型オメガ3脂肪酸(DHA+EPA)が制御できることを見出しています。
シス型オメガ3を使用するようになったのは、当初は天然トランス型オメガ3脂肪酸を使用していましたが、
高濃度投与に関わらず患者の血中濃度が上がらず、突然死することがありました。
4.血管平滑筋のSPC反応性を確認する実験
a. 実験の目的
- 血管平滑筋の細胞質カルシウム濃度および張力に対するEPA の効果証明。
- 血管平滑筋のSPC反応性に対するコレステロールの関与。
- SPC活性化と細胞膜ラフト(membrane raft)の関与。
実験では、血中コレステロール濃度とSPCの反応は正の相関を示し、
高脂血症治療薬(EPA製剤等)で血中コレステロール濃度を正常範囲内に低下させると、
血管平滑筋のSPC反応性が消失することが確認されています。
またコレステロール吸着剤であるシクロデキストリン(Methyl-β-cyclodextrin:MCD)で
脂質や蛋白質が筏状に局在する細胞膜ラフト(membrane raft)を除去すると、
SPCが活性を失うことも確認しています。
これによって、血管平滑筋のカルシウム非依存性収縮には、
コレステロールおよび細胞膜ラフトが深く関与することが示唆され、
高脂血症が心血管異常の主要なリスクファクターであることが理論付けられています。
b. 実験の方法
実験には高脂血症の実験用ウサギの腸間膜動脈平滑筋、人間の腸間膜動脈平滑筋および
培養冠状動脈平滑筋細胞が用いられました。
実験では血中コレステロール濃度と異常収縮原因物質のSPCの反応が正の相関を示し、
高脂血症治療薬(EPA製剤)で血中コレステロール濃度を正常範囲内に低下させると、
血管平滑筋のSPC反応性が消失することを確認しています。
この実験では、高脂血症の人はSPCによって血管異常収縮を示すであろうこと、
EPAは血管の異常収縮治療に有効であろうことが示唆されています。
また脂質や蛋白質が筏状に局在する細胞膜ラフト(membrane raft)を除去すると、
SPCが活性を失い、フィン(fyn)とローキナーゼ(Rho-kinase)が細胞膜に転位(translocation)しなくなる、
すなわち、これらの酵素が活性化されなくなるため、
血管平滑筋の異常収縮が起きなくなることが確認されています。
細胞膜ラフトの除去には実験用のシクロデキストリン(Methyl-β-cyclodextrin:MCD)を使用。
MCDの効果は、細胞膜ラフトの構成物質の一つであるカベオリン(caveolin-1)が除去される事で確認します。
また、GM1ガングリオシドという糖蛋白も細胞膜ラフトの構成成分の一つで、
コレラ毒素(cholera toxin subunit B (CT-B)に結合する性質があります。
蛍光標識したCT-Bを使用して、MCDによりラフトが除去される事も確認できます。
5. フィン(fyn)とは
フィン(fyn)はファミリーチロシンキナーゼ(Src)(Src family tyrosine kinase :Src-TKs)の 1つ。
1986年に発見された。
機能は、免疫細胞(Tリンパ球)の活性化や、神経細胞における受容体の働きを調節する事が報告されています。
6. SPCのシグナル伝達を担う2つの蛋白質とリン酸化酵素(蛋白質をリン酸化する酵素)
① Srcファミリーチロシンキナーゼ(Src family tyrosine kinase )(Src-TKs)
蛋白質を構成するアミノ酸のチロシンをリン酸化するチロシンキナーゼの1つです。
非受容体型チロシンキナーゼであるSrcファミリーチロシンキナーゼ(Src family non-receptor protein tyrosine kinase )は,免疫機構、神経活動、がんの増殖や転移への関与が示唆されています。
② Rhoキナーゼ(Rho-kinase)
蛋白質を構成するアミノ酸のセリンとトレオニンをリン酸化するプロテインキナーゼの1つです。
Rho-キナーゼは、血管平滑筋のカルシウム感受性増加に関与、異常収縮を介して狭心症や高血圧に、
また平滑筋細胞やマクロファージの遊走を介して動脈硬化病変形成に深く関与します。
7. 細胞膜ラフト(membrane raft)とは
スフィンゴ脂質およびコレステロールが豊富な細胞膜上の小さな部分(微小領域、ドメインと呼ばれています)。
脂質や蛋白質が筏状に局在するためにラフトと呼ばれます。
細胞膜ラフトを構成する主要な蛋白質であるカベオリンは、種々の細胞内シグナル伝達分子が
細胞膜ラフトへ集積するのを助けるアンカーとしての役割を果たし、
これらのシグナル伝達分子の細胞内局在や活性を調整しています。
従って、細胞膜ラフトは種々のシグナル伝達の分岐点・反応の場を構成し、
カベオリンは細胞内情報伝達のスイッチ役を果たします。
8. カベオリン(caveolin-1)とは
カベオリン‐1は細胞膜ラフトに局在するタンパク質です。
カベオラ(caveolae)という細胞膜構造物を構成する主要なタンパク質。
血管内皮型一酸化窒素合成酵素(eNOS)の調節に関与しています。
すなわち、刺激されていない内皮細胞では、eNOSは、カベオリン-1と結合する事によって、
その活性が抑制されており、また、カベオラに局在しています。
内皮細胞が刺激を受けると、細胞質のカルシウム濃度が増加し、
カルシウムによってeNOSとカベオリン-1との結合が阻害されるため、
eNOSはカベオラから解離し細胞質へ移動すると共に、活性化され、一酸化窒素(NO)を生成します。
NOは、ガスであるため、内皮細胞に隣接している平滑筋細胞の内部へ容易に移動し、
平滑筋を弛緩させるサイクリックGMPを生成する酵素(Gキナーゼ)を活性化する事によって、
血管を弛緩させます。
9. 一酸化窒素合成酵素(nitric oxide synthase:NOS)とは
一酸化窒素を合成する酵素(nitric oxide synthase)(NOS)には三種類が確認されています。
一酸化窒素合成酵素は体内の作動場所によりnNOS(neuronalNOS)(神経型NO合成酵素)、eNOS(endothelial NOS)(血管内皮型NO合成酵素)、iNOS(cytokine inducible NOS)(誘導型NO合成酵素)の3つのタイプに分けています。このタイプ別名称は nNOSをNOS1のように、1-3の番号を付けて呼ぶこともあります。
オメガ3脂肪酸のニュースと解説 の記事一覧
- パーキンソン病と脳神経変性疾患の抑制
- 「賢い子に育てる究極のコツ」その3 マアジ(真鯵)には養殖魚があります. 温暖化により北上する熱帯系メアジ、マルアジ
- 長寿社会の勝ち組になるには(その25): ポテトのクロロゲン酸とポテトスープの健康度:アヒアコとヴィシーソワス
- 医療新時代を開くナイアシン(NAD+ NMN)その3: 男性型脱毛症(AGA)は ナイアシンでプロスタグランディンD2の制御 ?
- シス型オメガ3脂肪酸がカルシウム非依存性の血管異常収縮を防ぐ: 高脂血症が関与する突然死。カベリオンとは
- 天然オメガ3脂肪酸と脂質メディエーターのレソルビン(Resolvin)とは
- 天然魚油のオメガ3脂肪酸はバイオ合成オメガ3とは 効果が異なります: 天然魚油のオメガ3脂肪酸が血圧安定に寄与する
- オメガ3過剰摂取は逆効果:国立がんセンター(その2)
- 鬱(うつ)には魚油が効果的: 国立がん研究センター松岡豊博士らのコホート調査
- 慢性化生理的炎症を軽減 天然魚油のシス型オメガ3