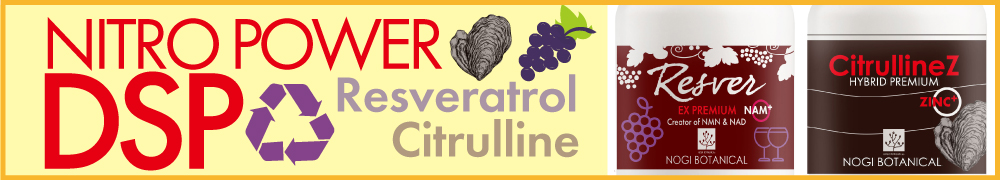1. 小泉、新農林大臣が把握していた米(こめ)流通の違法行為
2. 食糧法を機能不全にした米流通寡占化組織の存在
3. 炙り(あぶり)だされた意図的供給量制限(intentional shortage)
4. 100兆円を抱え金融機関と化したJA全農グループ
5. 意図的供給量制限の効果を増幅させる生産者の自家用米積み増し
6. 都市部の米生産農家に資産家が多い理由

1. 小泉、新農林大臣が把握していた米(こめ)流通の違法行為
米流通問題の専門大臣を自認する小泉進次郎農林大臣は、自民党 農林部会長(2017年8月)就任以来、与野党有志とともに、独禁法適用除外、金融機関機能付加などの超超特例で護られた、全国農業協同組合連合会(全農)の特権乱用を指摘していました。
今回の米価暴騰抑制に対する新農林大臣の矢継ぎ早の政策からは、米流通構造に違法行為の存在を確信していることが伺われます
食料管理法(1942年制定)が廃止され、米の流通自由化を標榜する食糧法(1995年~)に姿を変えましたが、何をやっても自由という自由市場経済となったわけではなく、上位法として「食料供給困難事態対策法」が制定され、市場監視をしています。
新農林大臣は米価格の短期的暴騰はその対象となると考えているのでしょう。
すでにこの法を適用するために「暴騰は異常事態」との公的発言を繰り返しており、品不足は不作、凶作、精米の低歩留まりが原因とする関係者の説明に納得していないことは明らか。
7万軒を対象に卸売業者、小売業者の取り扱い量(仕入れ量)、販売量、在庫量、高値待ちの在庫隠匿が疑われる大手生産者らの生産量、在庫量の聞き取りと、社内立ち入り調査の実施を明言しています。
2. 食糧法を機能不全にした米流通寡占化組織の存在
太平洋戦争直後の飢渇(きかつ)を米国に頼る混乱期に打ち出された様々な*主食管理特例政策(食料管理法)は、「国民の誰もが食せる供給量と低価格維持を目的」に米の生産者、集荷する農業協同組合、卸など分配企業に数々の特典を与え、それなりに機能していた必用政策でした。
国民の飢えを凌ぐ(しのぐ)米作奨励ベースの政治は各地の生産者、消費者に支持され、自由民主党が戦後70年間政治の中心となり続ける原動力となりました。
朝鮮戦争、東京オリンピック、万国博覧会などで復興が進み、高度成長期となると、米の生産や流通機構を独占的に仕切る組織の肥満化が目立つようになりました。
2024年からのわずか1年間で、米価が倍増以上となる違法行為を 悪びれることもなく代表者がマスメディアで肯定。独占、寡占的な立位置にいて、米の流通は自由市場経済の下(もと)と勘違いしている流通関係者の驕り(おごり)なのでしょう。
「食料供給困難事態対策法」が急遽、制定されたのも、パンや麺とは全く異なる米の本質を知らず、度が過ぎた価格で販売する流通業者対策と言えます。
米は大根、キャベツと異なり、永年、主食としている「国民の誰もが食せる低価格」を維持するために、75年間も政府が巨額の税金を投じてきた歴史的な主食材です。
3. 炙り(あぶり)だされた意図的供給量制限(intentional shortage)
米暴騰問題に対する新農林大臣の第一声は、米穀流通業界最大手の木徳神糧社が短期間で500%を超える営業暴利を得ていること。中国、米国、タイなどの支社が米の輸出入を支配していること。
米が日本人にとってどれだけ大事な食材であり、だからこそ、
「その流通価格を国家が監視し続けている」ことを、忘れたかのような、米穀流通業界最大手トップの独善的な振る舞いと、発言に、新農林大臣が違法摘発任務遂行を宣言したものでした。
新農林大臣は農林部会長以来の10年を超える調査と、大臣権限で得られる省内情報で、木徳神糧社が国民生活の困窮を招いている令和米騒動の中心的存在であることを確信したのでしょう。
炙り(あぶり)だされたのは木徳神糧社を頂点とした卸業者らによる意図的供給量制限:
intentional shortage(supply scarcity):インテンショナル・ショーテ-ジ。
新大臣はこれが暴騰の主因と喝破しているようですが、この行為は食糧法に触れるだけでなく、*独禁法違反が疑われる行為。
*15年前に全農の資材納入事業による肥料・農薬、農作業機器の高シェアが問題視され、民主党政権が(2010年:平成22年)独禁法の適用を検討したことがあります。
4. 100兆円を抱え金融機関と化したJA全農グループ
全農(JA全農)の24年産米の集荷量は179万トン 日本の米生産総量は約700万トンですから25%。
全農のマージンはわずかと言われますが、全農関与外で生産者から直接買い付けられる大量の米の流通経路は複雑であり、卸業者や各地農協の関与有無などの実態は、未公開部分が多く、理解することが出来ません。
現在の全農はコストパフォーマンスが高い金融機関機能に注力。
全農グループには食料生産者ではない金融機能利用の準組合員加入が特例として認められており、準組合員は全農金融機能最大の顧客層と言われています。
全農グループに蓄積された連結総資産額は、2020年3月31日時点で大銀行と並ぶ105兆円以上。
ただし、昨年末に明らかになった農林中央金庫の2兆円にせまる赤字は、資金運用(約50兆円?)などを任せている全農に大きな被害を与えていると言われています。
5. 意図的供給量制限の効果を増幅させる生産者の自家用米積み増し
2024年産の米の収穫量は前年比で増加したものの、都市部の需給逼迫は依然として続いています。
各地の生産者が保存する米の盗難頻発で明るみに出た、平均150キロともいわれる自家用米の積み増し在庫。
これに高騰期待の思惑による大量の隠匿在庫が加わり、推定総計20万トン以上ともいわれます。
この仮需創造行為が卸業者らの*「意図的供給量制限」(intentional shortag)の効果を増幅させていると推測されています。
6. 都市部の米生産農家に資産家が多い理由
TVの米騒動街頭取材でよく聞かれるのは「流通中間業者のマージン過多で生産者が困窮するのは許せない」ですが、果たして40万戸と推定される米生産農家は生活困窮者なのでしょうか?
減産手当といえる*交付金は十分といえないのでしょうか。
一般的な国民には、武家政治時代の過酷な年貢米取り立て、地主と小作人などがイメージにあるのでしょうが、農業生産者の経済的な地位はGHQの農地解放で様変わり。
農地解放後のインフレーションで、都市部周辺の土地価格は右肩上がりの高騰。
農地解放で耕作地を購入(激しいインフレでタダ同然)または、代々、農地を継承している都市部周辺の農家は一転して資産家。
都市計画、緑化計画への売却や(本来は禁止されている)副業目的の農地用途変更で、貸店舗、アパート、駐車場などの経営者が続出。
農家の財政が極端に2極分化した原因といわれますが、原則では用地変更禁止の都市部農地ですが、農協の支援による用途変更で減少が続いています。
*農林水産省は、米の生産者に対して、主食用米以外の用途(飼料用米、米粉用米など)への転換や、輸出用米の生産、付加価値向上、流通合理化などを支援する様々な補助金・交付金制度を設けています。
これらの制度は、米の需要減少に対応し、米農家の経営安定を図ることを目的としており、年間約3,000億円が支出されています。
健康と食品の解説 の記事一覧
- 麻薬のルーツは麻黄(Ephedra sinica:エフェドラ)のアルカロイド エフェドラ・アルカロイドから作られた神経毒のエフェドリン(ephedrine)
- 脳神経変性疾患予防と改善に世界最強の薬膳スープ 西の横綱はタイ庶民のトムヤム・スープ
- 世界の生牡蠣市場を盛り上げる日本のマガキ: これであなたも生牡蠣博士第一話:日本の生牡蠣とノロウィルス:30年間生産量が増えない世界牡蠣養殖何故?
- 健康寿命を延ばす若返り第2話 WHOが健康被害を招く合成甘味料のメタアナリシスを公開:異性化糖が腎疾患と老化を促進するAGEを産生
- 長寿社会の勝ち組となるには(その16): 医者により廃人にされた腎不全患者:偽AI健康情報にご注意 ChatGPで良質な健康情報が得られるか
- カリフォルニア州が目指すアクリルアミド含有食品排除
- 長寿社会の勝ち組となるには(その1):健康オタクが癌になり、認知症を防げないなぜ 健康オタクの盲点:サプリメントの危険性は化学合成素材と過剰な摂食量
- 健康寿命を延ばす若返り第4話: 水産、食肉加工品が添加する亜硝酸塩(亜硝酸ナトリウム)
- 健康寿命を延ばす若返り第1話: 農水産生鮮食品の保健効能表示ができないわけ
- 健康寿命を延ばす若返り第1話 農水産生鮮食品の保健効能表示ができないわけ