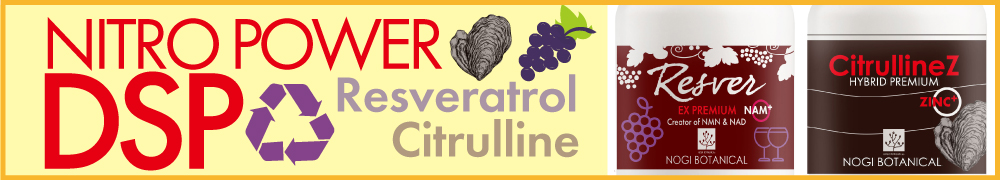1. 神話となった、「オメガ3は摂れば摂るほどリスクが下がる」
先回ご紹介した「魚介類・オメガ3系脂肪酸摂取とうつ病」の
コホート調査では、魚介類やオメガ3系脂肪酸は
「摂れば摂るほどリスクが下がる」というような関連ではなく、
ある量でリスクが下がり、それ以上摂ると影響がみられなくなることが
示されました。
学者の試験管内実験やマウスなど動物実験では三桁の倍数で使用されることもある
材料も、疫学実験では一般的投与量をやや上回る程度。
疫学的調査は安全性のために、少なめの投与ですから、
非常に大事な発見と考えねばなりません。
これまで常識のように考えられてきたことが、蛋白質化学、分子細胞学、
遺伝子工学等の発展に伴う分析機器、計測機器、顕微鏡などの進化により
真逆の考え方を要するケースが増えています。
作用機序が明らかになるに連れて、医薬品、サプリメント、食材の
適正摂取量に対する考え方にも大きな変化がみられるようになりました。
https://nogibotanical.com/archives/1748
2. タンパク質分析方法の進化
2. タンパク質分析方法の進化
生命科学のタンパク質科学、構造生物学ではタンパク質の質量や構造の
解明が加速度的に進んでおり、この2年をみてもこれまでの医学医療の常識が
次々に覆されています。
2002年のノーベル化学賞は田中耕一博士の質量分析(Mass Spectrometry, MS)
『生体高分子の画期的分析手法の開発』
2017年のノーベル化学賞は米国人グループ「溶液中の生体分子の構造を高い解像度で
観察できるクライオ電子顕微鏡(cryo-electron microscopy)の発明」でしたが
その成果が大きく貢献しています。
https://nogibotanical.com/archives/5324
3. 化学合成オメガ3と天然オメガ3の違い
オメガ3サプリメントはバイオ合成原料が圧倒的に増えてきましたが、
食生活のベースは天然の魚類由来オメガ3脂肪酸。
合成オメガ3は効能、効力が違いすぎますので摂取量を天然とは比較はできません。
魚油そのものからの天然オメガ3は、魚油からの全成分を加えれば、合成オメガ3の
5-10分の1くらいでも合成オメガ3が持つ機能をカバーでき、魚油の様々な効能が
追加されて加わります。
いわし、さば等の青魚、サーモンの魚油に多く含まれるオメガ3脂肪酸は
魚油のビタミンA, D、E などと共働して、さらなる効果を発揮します。
人体や魚油の過酸化を防止する最大の抗酸化物質は魚油に多く含まれる
天然のビタミンE。
この酸化防止機能は合成オメガ3脂肪酸に合成のビタミンEを
添加しても機能しません。
https://nogibotanical.com/archives/5324
オメガ3の長期摂取による安全性は、食材からの日常的摂取量を基準に
推定しています。
多くの疫学的調査によれば日常的摂取量で、様々な効能が確認されています。
4. 適正な脂肪酸バランスとは
脂肪酸バランスの目安比率は肉脂、パームオイル、ココナッツオイルなどの
飽和脂肪酸1、オメガ9など一価不飽和脂肪酸1.5、リノール酸、魚油など
多価不飽和脂肪酸1が理想といわれます。
多価不飽和脂肪酸のなかではオメガ3が1に対してオメガ6は
2から4の比率が推奨されていますが、すでに加工食品の40%以上が使用する
「植物性油脂」により、リノール酸(オメガ6)の摂取量がとびぬけて大きく、
危険水準をはるかに超えています。
最近では多くが1:15近くまでのバランスとなっているといわれます。
「脂肪と脂質をもっと詳しく知ろう 」
https://nogibotanical.com/archives/5324
一般的にはマグロトロやイワシ、鮭類ならば100gの生食摂取で
500㎎から2,000㎎の天然オメガ3が摂取され、1日の必要量が
満たされるといわれますが、天然マグロのトロは高価すぎますので
現実的ではありませんから除外。
青魚や鮭に較べダイオキシンの危険性が高いこともあり、常食はお薦めできません。
青魚や鮭の刺身ならば500㎎から1,000㎎の天然オメガ3を
摂取することが出来ますから十分です。
(養殖魚は産地により異なりますが、常に抗菌物質の危険を考えねばなりません)
*100㌘の魚は小型の鯵(アジ)や中型の鰯(イワシ)2匹ぐらいの
頭、骨を除いた可食部分
5. 崩れた脂肪酸バランスを改善するのはオメガ3脂肪酸
オメガ3脂肪酸必要量を按配する要素(ファクター)は
高血圧、糖尿病など持病をお持ちの方や、食習慣、年齢、体格、遺伝子、
生活環境などが影響しますから、必要量は千差万別。
簡単に決めて良いものではありませんが、魚油の天然オメガ3に
関しては日常的なオメガ6脂肪酸の摂取量から推量するのが良いでしょう。
オメガ3脂肪酸摂取量を(一般的な標準より)増やすことが
出来る(増やす必要がある)のはオメガ6の過剰摂取が激しい方です。
ほとんどの方はオメガ6の過剰摂取で脂肪酸バランスを
崩しており、下記はオメガ3を大きく崩す要因のいくつかの例ですが、
オメガ6摂食量が多いと思われる方はオメガ3の増量が必要でしょう。
下記の食習慣がある方はオメガ6摂取が過剰となっています。
*食品表示ラベルに植物性油脂と表示されている
加工食品を愛用している方。
例:冷凍食品、揚げ物、
スナック菓子、ミルクチョコレート、アイスクリーム、
ラクトアイス、マーガリン使用のパンや洋菓子。
*中華料理、カツレツなどの外食が多い方。
*あまり家で料理を作らず、スーパーなどのデリカや
総菜売り場を利用する方。
*大豆油、トウモロコシ油、混合サラダ油を揚げ物に使用している方
これらの摂取に気配りし、減らしている方は真逆にオメガ3の
必要量が減少します。
6. 天然オメガ3の効用を促進する食生活
脂溶性のビタミンA、E、K、脂肪酸バランスの維持に
必要なオメガ9が豊富なごま油、天然セサミン類、サメ肝油のスクワレンは
天然のオメガ3とともに摂食すれば相互作用によって双方の効能が高められ、
少量で済みますから、長期的な安全性をより確保できます。
天然の魚油を日常的に摂取されている方はビタミンA、ビタミンEなどの
ビタミン類やミネラルなど補酵素的役割をする物質を個別に摂る必要が
ありません。
魚油などの天然の脂溶性ビタミン類は単機能の化学合成ビタミン類と異なって
同じビタミンA、E、K、といえども構造が少しずつ異なる物質群で
構成されています。
(エパフレッシュは含有量を増やしても問題ないと思われる天然ビタミンE類は
増量しています)
7. 効果を減ずるオメガ3のトランス脂肪酸と過酸化脂質
天然オメガ3が豊富とはいえ、鮮度が落ちた魚や魚油は過酸化脂質が
健康を著しく害します。
焼き魚など加熱調理ではトランス脂肪酸、アクリルアミドが生ずる温度と
焼き加減に慎重な配慮が必要です。
また外光(太陽光、照明)に曝されたサラダ油や加工食品は
植物性不飽和脂肪酸が過酸化します。
https://nogibotanical.com/archives/4270
8. 飽和脂肪酸の代替品がオメガ6となる危険性
食生活における脂肪酸バランスは飽和脂肪酸を10%以下に抑え、
不飽和脂肪酸を15%以上にするよう指導されていましたが、欠陥が
目立つようになりました。
多くの保健ガイドラインも時代により変化せせるのは当然と思われますが、
現行の基準となるのは半世紀前に決められたガイドライン
(飽和脂肪酸を5%‐10%に抑え、不飽和脂肪酸を15%程度に増やす)です。
ガイドラインが、工業化、大量生産による食用油、油脂の変化に
同調していないのが問題と、アメリカ厚生省のラムスデン博士は指摘しています。
半世紀前に比べ不飽和脂肪酸のバラエティーは格段と拡がっており、
生産の工業化により健康を害する食用油、油脂が増え、
トランス脂肪酸、過酸化脂質の害が加わっていることも博士らは指摘しています
https://nogibotanical.com/archives/1212
*アメリカ厚生省(National Institutes of Health)
クリストファー・ラムスデン博士(Christopher Ramsden, MD.)
オメガ3脂肪酸のニュースと解説 の記事一覧
- パーキンソン病と脳神経変性疾患の抑制
- 「賢い子に育てる究極のコツ」その3 マアジ(真鯵)には養殖魚があります. 温暖化により北上する熱帯系メアジ、マルアジ
- 長寿社会の勝ち組になるには(その25): ポテトのクロロゲン酸とポテトスープの健康度:アヒアコとヴィシーソワス
- 医療新時代を開くナイアシン(NAD+ NMN)その3: 男性型脱毛症(AGA)は ナイアシンでプロスタグランディンD2の制御 ?
- シス型オメガ3脂肪酸がカルシウム非依存性の血管異常収縮を防ぐ: 高脂血症が関与する突然死。カベリオンとは
- 天然オメガ3脂肪酸と脂質メディエーターのレソルビン(Resolvin)とは
- 天然魚油のオメガ3脂肪酸はバイオ合成オメガ3とは 効果が異なります: 天然魚油のオメガ3脂肪酸が血圧安定に寄与する
- 鬱(うつ)には魚油が効果的: 国立がん研究センター松岡豊博士らのコホート調査
- 慢性化生理的炎症を軽減 天然魚油のシス型オメガ3
- 重篤な敗血症を魚油の脂肪酸が改善する