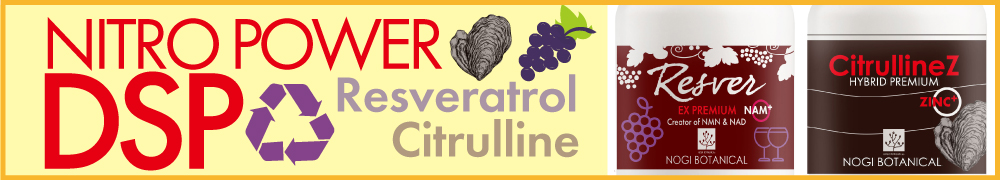世界的に欺瞞が絶えない食品、食材業界と上手に付き合い、健康生活を維持する手法を
提言するシリーズを続けていますが、今週は米国科学アカデミーの安全性宣言とも
とれる唐突な発表を機会に最大の遺伝子組み換え作物である大豆を取り上げました。

グリーンが遺伝子組み換え作物導入国.米国大陸が圧倒的に多い.
アイコンは導入作物(米国農務省)
1. 米国科学アカデミー有志が遺伝子組み換え作物の安全性を強調
2016年5月16日に米国科学アカデミー( US National Academies of Science)の
有志研究者(約50名)らは「遺伝子組み換え作物(GM:genetically modified organism)
が在来品(conventionally bred crops)に較べ危険であることを示すなんらの
確証も得られなかった」と*発表しました。
*Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects
これは遺伝子組み換え作物(GM)の安全性に関する約20年間の研究論文(約900本)を
精査した結果によるとのことですが
農業関連の遺伝子組み換え作物は生産が始まってまだ20年。
100年はかかるだろう安全性の確認が現段階でわかるはずはありませんから
唐突ともいえる米国からのこの報道は関係者を驚かせています。
モンサント社がトマトなどの組み換え農産物を発表し、大規模栽培が始まった
1996年頃から賛否の議論が沸騰し始めましたが
米国科学アカデミーはこの報告で「遺伝子組み換え作物に疑義的な諸国は
製造方法の安全性ではなく、収穫された作物そのものを良く調べてほしい」と
要望しています.
ただし、薬剤耐性を得ている害虫や雑草の問題点だけはマイナス要素と指摘。
政府と関連企業寄りのプロジェクトではないと思わせる装飾がなされています.
2. 米国科学アカデミーがこの問題を取り上げた意図は?
米国科学アカデミーは内外の功績のある学者たちが首都で結成している任意団体。
アカデミーメンバーの著名な米国学者たちは政府とも密接な関係がありますから
このプロジェクトが学者たちの純粋な正義感から発足したとは考えられません。
大統領選挙が近くなり、(当選の可否は別としても)大企業寄りの共和党の存在感が
増していることとの関係も否定できませんし、生産が始まって15年を超えても
先進諸国への普及スピードが遅いこと、
最大輸出量のGM大豆輸出がここ10年間伸びないことに米国農業界の焦りが
感じられる報告ですが、その背景はいろいろ推定できます。
(参考)遺伝子組み換え作物の歴史などを紹介しています(一部は重複).
「遺伝子組み換え作物が否定される何故(なぜ):
15年続いている安全性疑惑」
https://nogibotanical.com/archives/4266
3. 日本の大豆市場には遺伝子組み換え大豆が溢れています
遺伝子組み換え食品摂食量が最も多いのは大豆、トウモロコシなどを使用する食用油経由。
日本人が使用する大豆は大半が米国からの輸入大豆です。
輸入大豆も米国からは「非遺伝子組み換え大豆」が増えていますが
遺伝子組み換え大豆は消費者用の混合サラダ油のみならず、醤油、豆腐、納豆、
チョコレート、アイスクリーム、ケーキ、ラーメン、おせんべいなど幅広い加工食品に
使用されています。
トウモロコシ、キャノーラ(菜種)、じゃがいもなどの遺伝子組み換え作物を加えれば。
加工食品の40%以上が何らかの組み換え作物を使用していますから
避けることは至難でしょう。
また飼料用にも大量の遺伝子組み換えトウモロコシが使用されており間接的に
影響を受けるといわれます。
また「非遺伝子組み換え」を表示する加工品も詐称、偽称で相当量の遺伝子組み換え大豆が
使用されているようですから避けることは至難というより不可能ともいえます。
対策:
*出来るだけ「地産地消」食品を心がけること。
大手の食品、飲料、添加物製造販売会社は大量の原料調達が必要です.
大量の均質原料調達のコストを考慮すれば3,000億から6,000億円/年の
遺伝子組み換え作物を海外から輸入せざるを得ないのが現状。
食品表示が詳細、明解で信用できる。地域に根付いた歴史と経営者に信頼性がある。
このような小規模製造会社の商品を選択することが賢明でしょう。
*加工食品の食品表示に「植物性油脂」と書かれた商品を避けること。
https://nogibotanical.com/archives/2321
*外食では油脂、ショートニング、食用油使用量の少ないメニューを選択すること。
*ごま油、米油、菜種油など国産が明白なブランドを使用したメニューや
加工食品を選択すること
*チョコレートやクッキーなどの加工食品はバター使用のヨーロッパ製がより安心。
オリーブオイルは遺伝子組み換えの恐れはありませんが、輸入品がほとんどで
船で運ばれた安価な製品には過酸化脂質の害があります。
イタリアン、スパニッシュ料理の外食は要注意です。
https://nogibotanical.com/archives/4270
*大豆は健康食品として優れた機能を持ちますが、それだけに強い有害性があります。
日常的な摂食量を大幅に超えないことです。(解説は後日に別途)
4. 遺伝子組み換え作物に対する日本の立ち位置
国際的な安全性評価基準は2000年から2003年までに*コーデックス委員会に
おいて作られていますが、日本はこの委員会において、中心的な役割を果たしている
遺伝子組み換え推進先進国と言えるようです。
国内での栽培は禁止していますが加工食品用、飼料用のGMは世界でも有数の輸入国です。
(*食品の安全性と品質に関して国際的な基準を定めています)
日本は米国との友好関係維持が外交の大前提であり、
公然と遺伝子組み換えに異議を唱える関係者は少数派ですが
金権思想が強い米国の営利会社とは一線を画すべきで
政治問題と国民の食の安全を護ることとは切り離すべきでしょう。
組み換え食品の可否は「議論が多い割には、安全であることの研究報告が少ない」
といわれます。
大部分の消費者がGM食品と品種改良食品との区別ができていませんから
少なくとも安全性を確保するにはどうすべきかの指針が必須。
日本では行政が「農産物で永年継続されている品種改良と何ら変わりない」と
解説しますが、それに不信感を持つ人が少なくありません。
組み換え農産物の輸入は認可制ですが、その安全テストが公平であり
信頼できるかどうかは議論のあるところです。
トクホも含め食品の安全性、有為性は行政任せを避け消費者個々が判断するべきでしょう。
細胞レベルで強制的に遺伝子を操作する組み換えと、農産物改良研究者が花粉操作などで
作る品種改良とは根本が異なります。
植物の成分組成を人為的に組み換え、一部を除去(改変)、
体に良いと思われる成分のみを選別して造られた合成食用油も開発されていますが、
本当の意味の安全性の確保はなされていません。
https://nogibotanical.com/archives/2336
5. 遺伝子組み換え作物の安全性は現段階で得られるのでしょうか?
アフリカ諸国などがGM必要性の「錦の御旗」となっていますが、
飢餓が蔓延している後進各国と飽食の先進国、新興国とは議論が異次元。
「標準的な食生活(適量)ならば数百年間以上問題が無かった食品」が
本当の安全とするならば、GMは安全性の確認が当分できないといえるでしょう。
米国科学アカデミーで調査報告を作成した学者たちも、真の安全性が数十年程度で
確認できるとは考えておらず、組み換え食品の輸出振興政策に寄与しているという
スタンスのような気がします。
経済性最優先のGMO素材開発会社や、普及させたい米国や日本政府の安全性解説には
いまだに人工胃液、腸液や動物実験に基づいたものも多く、人間の摂食期間実績もまだ
数十年。
選択肢の多い日本国民に、安心して摂食しろと言われても無理があります。
これまでに実用されている安全性の確認は、組み換え食品と非組み換え食品の
構成成分を比較しています。
構成成分に大きな差が無いときに
「全般的に同等」(substantially equivalent)という表現で安全と
みなしていますが、
この場合は動物実験などが無いままに特許が与えられているといわれます。
保険会社も将来予想される損害賠償の危険性を認めて、消極的といわれます。
EUは、すべてのGMOは既存の食品と同等でない
(”no longer equivalent to traditional food”)と判断しており、
EUで承認されている大豆とトウモロコシについては、1139/98の規制に基づき
表示を義務づけています
6. 米国産大豆の世界一を猛追するブラジル
アメリカは、世界最大の大豆生産国で、想像も出来ない広さの
耕作面積(75.0 million acres:2011年)を持っていますが
2011年の収穫量は3,329 million bushels*
*アメリカ・ブッシェル:約35リットル:大豆は約27.2㎏
遺伝子組み換え(GM)生産量は頭打ちで何年も大きな変化はありません。
世界の大豆総生産量は3億トンを超えますが、その60% くらいが
遺伝子組み換え大豆。
ピーク時には米国の総生産量が世界の半分以上もありましたが
現在は約35%に落ちています。
現在の米国の生産は遺伝子組み換え大豆がほとんどで、その40%以上が自国消費.
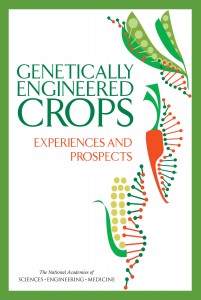
アメリカ(米国)産大豆は収穫の45%以上が丸大豆、大豆粕、大豆油として
輸出されていますが、かっては輸出が50%を超えていました。
アメリカ政府は1973年と1980年に政治的な大豆の輸出禁止措置をとりましたが
これが失政策。
大手輸入国の日本やソ連(現ロシア)がブラジル、アルゼンチンなどを代替国として
開発したために世界シェアが低下してしまいました。
現在でも米国はトップですがブラジルが迫っており、代替両国の合計は米国を
上回るようになりました。
世界の健康と食の安全ニュース の記事一覧
- 新浪サントリー会長の麻薬常習疑惑と日米のオピオイド危機
- レスベのスチルべノイドが防御する微生物感染症: スチルべノイドが免疫細胞強化ペプチドのカテリシジンを活性化
- トランプ大統領の医療行政改革は日米の赤字財政改善の鍵 「日本は相互関税の対抗措置をとるべき」ではありません
- トランプ大統領の過激な宣伝フレーズ 新時代の緻密なマーケッティング・テック駆使
- トランプ大統領がWHO脱退を即決した背景 太平洋戦争戦勝国のおごりと黄昏(たそがれ)
- トランプ政権のNIH再編成とWHO脱退の荒療治 赤字財政の主因である日本の医療制度、改革が大進歩
- 究極の©オールインワン・メッド(AOM)はフォシーガか、ツイミーグか
- 世界の生牡蠣市場を盛り上げる日本のマガキ: これであなたも生牡蠣博士第一話:日本の生牡蠣とノロウィルス:30年間生産量が増えない世界牡蠣養殖何故?
- 認知症抑制タンパクNrf2を活性化する旧仏領インドシナの花食文化(2) 脳神経変性疾患の予防にベトナムの鉄人花鍋
- 長寿社会の勝ち組となるには(その16): 医者により廃人にされた腎不全患者:偽AI健康情報にご注意 ChatGPで良質な健康情報が得られるか